 |
ぶりの貝焼きとてりやき |
 |
 |
 |
島根県八束郡美保関町
貝焼き=資料館 「浜延舎(はまのや)」 てりやき=旅館「福間館」 |
|
 |
| ◇ぶりの貝焼き◇ |
 |
 |
 |
簡単な料理だが、なんともぶりと海苔がマッチして、最高の肴である。 |
|
 |
| =3人分= |
| 寒ぶりのはらみ |
60g位 |
岩のり(乾燥)
(かもじのり) |
5g位 |
| あわびの殻(大) |
3個 |
| こいくちしょうゆ |
大匙2 |
| 酒 |
大匙2 |
| 砂糖 |
適量 |
炭火
(ガスコンロ代用可) |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
|
|
 |
| 1. |
寒ぶりは、三枚に卸して皮をひいておき、はらみの部分をサイコロ状に切っておく。 |
| 2. |
あわびの殻は、良く洗い穴の部分を小麦粉を水で練ったもので止めておく。 |
| 3. |
あわびの殻にぶりの切り身、岩のりを入れる。
(岩のりが無い場合は市販の海苔の佃煮で代用する) |
| 4. |
そこに調味料を合わせたものをかけて混ぜ合わせ、火にかける。
(炭火のコンロが最適だが、無い場合はガスコンロでも良い) |
| 5. |
味を見ながら箸でかき混ぜ、水気が無くなるまで煎りつける。
(焦げ付きそうになったら、酒を加えてのばす) |
| 6. |
すき焼きのように材料や調味料を足しながら熱々を頂く。 |
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
| ◇ぶりのてりやき◇ |
 |
 |
 |
一般的なぶりのてりやきより、さっぱりとしている。漁師料理に近い味である。 |
|
 |
| =3人分= |
寒ぶりの切り身
(大きめに切る) |
3切れ |
| たまりしょうゆ |
適量 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
| 1. |
卸したぶりの切り身を少し焦げ目が付く程度に焼く。特に皮を良く焼く。 |
| 2. |
熱い内に焼いた切り身を、ボールなどに入れた、たまりしょうゆの中に入れからめる。 |
| 3. |
皿に盛り、すだち、ゆずなどを添えて出来上がり。 |
 |
 |
|
|
|
|
 |
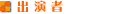 |
| 福間 隆 (主人) |
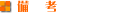 |
島根県の美保関は、島根半島の東端に位置する風光明媚な町で古代の壮大なドラマが残るところである。
有名な美保神社のお社は「美保造り」と呼ばれ、国の重要文化財に指定されており、ご祭神である事代主神は、ゑびす様であり、全国各地に在るゑびす社3385社の総本社として、ことに水産、海運に携わる人々から広く尊い親しまれている歴史がある。今も、漁に出かける猟師たちは、湾内で大漁と安全を祈願する儀式を忘れない。
美保関は、江戸中期以降北前船の西回り航路の各国の物産の集散積載地として松江幡のもと、50軒近い海鮮問屋が並び盛況であったと言う。当時の海石を切り出して舗装に使った石畳の道が当時の面影を残している。 |
 |
<ぶりの貝焼き>
「貝焼き」も、その北前船によってもたらされたと思われ、北海道からの日本海側では、似た様な貝焼きの料理が沢山存在している。島根では、宍戸町の八雲本陣の「カモの貝焼き」が有名だが、港町の美保関では、魚を使ってアレンジされたのかもしれない。資料館「浜延舎(はまのや)」は、明治初期の民家を改造したものだが、江戸から明治にかけては、北前船の船員の旅籠として使われていたそうである。船乗り、猟師が酌婦とともに、この「貝焼きを」肴に各地の情報を交換しあった情景が偲ばれる。 |
|
 |
 |
 |
 |