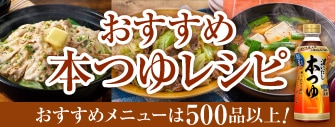梅干し
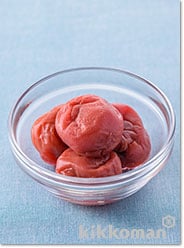
旬6~8月
梅の実は梅干し、梅酒、梅ジュース、梅ジャムなどに。
梅干しは、肉や魚のくさみ消しとして煮物、焼物のほか、ご飯料理、たれやドレッシングに加えても
- 栄養
-
梅の酸味は、クエン酸、リンゴ酸などの有機酸によるものです。クエン酸はエネルギー代謝をすすめて疲労回復や老化を防止し、食欲増進効果も期待できます。抗菌作用があるので、食べ物の腐敗を防ぎ、お腹の調子を整えるといわれています。ビタミン、ミネラルも含まれています。
- 目利き・保存
-
梅の実に傷がなく、みずみずしく、はりのあるものが良品です。梅酒や梅ジュースには若い青梅を。梅干し用には熟して果皮がほんのりと黄ばんだものを使います。鮮度が大切なので、手に入れたらできるだけ早く加工しましょう。梅干しは粒がそろって、色むらのないものが良品です。昔ながらの梅干しは常温で、減塩タイプは冷蔵庫で保存しましょう。
- 調理のヒント
-
梅の実は梅干し、梅酒、梅ジュース、梅ジャムなどに。しょうゆ漬けにした「梅しょうゆ」も手軽につくれておいしいので、重宝します。青梅の種には青酸を生成するアミグダリンという毒性成分が含まれているので、青梅の生食は避けましょう。梅干しは、肉や魚のくさみ消しとして煮物、焼物のほか、ご飯料理、たれやドレッシングに加えてもおいしくいただけます。



 10分
10分 87kcal
87kcal 1.9g
1.9g