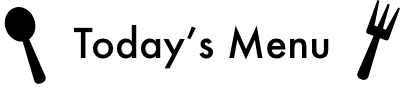
【プロ直伝】基本の餃子の
レシピ・作り方。
皮からでも意外と簡単!

おうち中華の定番メニューのひとつ、餃子。手作りのこだわりどころはいろいろありますが、お店の味を目指して皮作りからチャレンジするのも楽しいものです。今回は“超料理マニアの料理人”東山広樹さんに、想像以上に簡単にできる「皮から作る自家製餃子のレシピ」を伝授してもらいました。作り方や焼き方のポイントに加え、「味変たれ」もご紹介。手作り餃子をいつも以上においしくする、プロならではのコツが満載です!
餃子作りのプロが教える
3つのコツ
東山さんに教えてもらったレシピには、おいしく作るためのポイントが随所に散りばめられています。特に意識したいコツを皮作り、肉あん作り、焼き方の3つの工程からピックアップ!
 皮から手作りする餃子は計量が大事
皮から手作りする餃子は計量が大事
皮の伸びやすさや食感は、生地の材料となる小麦粉と水の量に大きく左右されます。それこそ1g単位で変わってくるので、計量はしっかり行いましょう。肉あんの材料もきちんと量ることで、皮の枚数にぴったりの量を作れます。ひき肉を使い切りたいときも、肉あんの分量から小麦粉と水の重さを逆算すればムダが出ません。
 肉あんにはラードを使い、乳化するまでしっかり混ぜる
肉あんにはラードを使い、乳化するまでしっかり混ぜる
肉あんに脂をしっかり加えることで、存在感のある手作りの皮にも負けない、ジューシーな仕上がりになります。サラダ油など、液状の油を混ぜ込むとべたつきやすく、食感も変わるため、ラードがおすすめ。肉としっかり混ぜ合わせて乳化させれば、かんだときに肉汁がじゅわっと広がるジューシーな餃子になります。
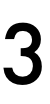 蒸し焼きの工程では、きちんと計量した湯を使う
蒸し焼きの工程では、きちんと計量した湯を使う
焼き目を付けた後は、火を通すために蒸し焼きにします。このとき、水を使うとフライパンの温度が上がるまでに時間がかかり、皮が溶けてベチャッとした仕上がりになるため、沸騰させた湯を使いましょう。湯の量も意外と重要で、多ければべたつき、少ないと粉っぽくなるため、きちんと計量することが大切です。水で計量しても沸かすと量が減ってしまうので、沸いた湯を計量する。これを覚えておいてください。

「僕がレシピを作るうえで最も重要と思うのは安全面、つまり家庭で食中毒を出さないこと。きちんと計量して大きさをそろえるのも、焼きムラによる生焼けを防ぐのが大きな理由なんです」と、東山さん。今回のレシピ考案にあたっては、できるだけ簡単に作れることを目指し、数え切れないほど試作してくれたそうです。
基本の餃子の作り方
皮から作る際の大まかな流れは、「皮の生地を作る」「肉あんを作る」「生地を伸ばして皮を作り、肉あんを包む」「焼く」の4つ。皮は伸ばしてから時間が経つと包みにくくなるうえ、味も落ちてしまうので、肉あんを先に作ってから皮を仕上げます。
今回の材料はとてもシンプル。皮に使う小麦粉は中力粉だけで、粉:水の比率も2:1と作りやすい比率です。餃子の皮には中力粉のグルテン含有量が最適ですが、薄力粉と強力粉を1:1の比率で合わせても近い食感が得られるのだそう。ちなみに、東山さんおすすめの中力粉は、株式会社日清製粉ウェルナの『日清 雪』。おいしいのはもちろんのこと、手に入りやすいのも魅力とのことです。
肉あんに使う野菜はにらのみ。香りとフレッシュさを備えているため、にんにくや白菜などを入れなくても満足できます。ひき肉は牛だと香りが強く不向きなので、豚100%がおすすめです。


上が皮の材料、下が肉あんの材料。肉あんの味つけはオイスターソースとこしょうでシンプルに。基本的にはこれだけの食材で、おいしい餃子が完成します!
材料(3人分・15個分)
- 【皮】
-
- 中力粉
- 200g
- 塩
- 小さじ1/2
- 水
- 100ml
- 【肉あん】
-
- 豚ひき肉
- 200g
- にら
- 100g
- ラード
- 60g
- オイスターソース
- 大さじ1 と1/2
- こしょう
- 適量
- 片栗粉
- 適量
- 水
- 適量
- サラダ油
- 大さじ1
- 湯
- 160ml
皮の生地の作り方

- ボウルに中力粉、塩を入れ、まんべんなく混ぜる。


先に小麦粉と塩を混ぜることで、塩が全体にいきわたります。水を入れてからだとムラが生じるので避けて。

- 水を入れ、全体がそぼろ状になるまでかき混ぜる。


小麦粉と塩、水を混ぜ合わせるための「水回し」と呼ばれる工程。広げた指の先で、ゆっくり大きくかき混ぜます。ボウルに付いた粉も、すべてこそげとりましょう。

そぼろ状になった生地。
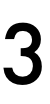
- 親指の付け根下にあるふくらみ(母指球)を使い、生地を軽くこねながらまとめる。


計量の工程をムダにしないよう、生地は余さずまとめてください。ボウルの内側や手に付いた生地もお忘れなく。


ボウルの内側はもちろん、手に付いた分もこすり合わせてまとめる。
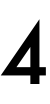
- 生地をテーブルや調理台などの上に置き、体重をかけながら手のひら(母指球)を前方にすべらせて、伸ばすようにこねる。打ち粉はしないのがポイント。



こねるときにまな板や敷いたビニールの上などで作業するとずれてしまうので、アルコール消毒をした清潔なテーブルや調理台に直接生地をのせます。打ち粉は生地に含む粉の分量が増えてしまうのでしないでください。
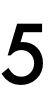
- ボソボソしていた生地がなめらかになり、表面がすべすべになるまで3〜4分ほどこねたら、団子状に丸めてラップで包み、冷蔵庫で1時間以上寝かせる。



表面は、しわのない状態に丸めましょう。また、生地は寝かせることで、水分が均等に分散される現象「水和(すいわ)」が進みます。寝かせてから1時間ほどで次の工程に移るなら、常温に置いていても問題ありません。冷蔵庫に入れれば3〜4日保存できるので、多めに作っておくのもおすすめ。
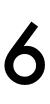
- 寝かせた生地を両手のひらで挟んで転がした後、テーブルなどの上で転がしながら伸ばす。



生地を棒状に伸ばす作業は、何度もこねたりせず、できるだけ一度で済ませるようにしましょう。伸ばした後にやり直すとしわが入り、皮を成形したときにそこから割れやすくなります。

親指と人差し指で輪を作ったくらいの太さになれば、伸ばす工程は終了。写真は目安のサイズで、直径約3cm×36cm。
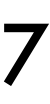
- 生地を4等分にカットし、計量しながら20gずつに切り分ける。



小麦粉と水を足した生地の重量は300gなので、15個に分ける計算。1本丸ごとから切り分けるより、4つに分けてからのほうが20gの見当を付けやすくなります。1/4サイズは75gで、それぞれ15g分の生地が余るので、計量しながら20gずつにまとめましょう。
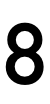
- 余った分をまとめた生地は、少量の水で湿らせた手で丸めて団子状にする。


小分けにした状態でも、ラップでぴっちり包めば3〜4日の冷蔵保存が可能。
肉あんの作り方

- にらを適当な幅にカットする。


刻む幅は、ざっくり1mm〜10mmの範囲内が目安ですが、東山さんによると「包めるサイズなら好みでOK」とのこと。細かいほど、肉と一体化してなめらかなあんに。歯ごたえを出したいなら、15mmくらいに刻むと、にらの存在感がグンとアップ!

左が約15mmに刻んだもの。ここまで違うと、味の印象も大きく変わる。

- にら以外の材料を入れ、ゴムべらなどで練り合わせる。


ジューシーな餃子に仕上げるために、粘りが出るまでしっかり混ぜて乳化させる。
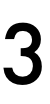
- にらを加えてさらに練る。


にらの比率が高いレシピなので、にらが飛び出さないよう、ゆっくりと混ぜましょう。にらが均一になり、全体がハンバーグの種くらいまとまるようになったら、混ざり合った合図です。

肉あん全体が混ざり合った状態。
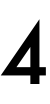
- 計量して25gずつ取り、俵形に丸める。


この工程を経ることで、包むときの効率が圧倒的に良くなります。計量しておけば、肉あんが皮からはみ出すこともなく、皮が汚れたり手直しに時間がかかったりする心配もありません。横長の餃子の形に合わせた俵形とすることで、より包みやすくなります。

15個分の肉あん。このまま鶏ガラスープの具にしたり、ゆでてポン酢と食べたりしてもおいしい。
包み方

- テーブルなどの作業台と、包んだ餃子を置くバットに片栗粉を振る。めん棒には片栗粉をすり付ける。



打ち粉をすることで皮がくっつきにくくなり、作業がスムーズに。片栗粉は小麦粉よりも粒子が細かいため、より扱いやすくなります。包んでいるうちに打ち粉が減ったら、その都度、足すようにしましょう。

- 生地を円形に整え、テーブルなどの上に置いて手のひらで軽くつぶす。



生地が切ったままの状態だと、つぶしたときにいびつな形となります。そこから伸ばしても皮の形はゆがんでしまうため、先に整えておくことが大切。


生地をつぶす前に整えることで、きれいな円形の皮ができる。
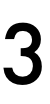
- 小さいめん棒で縦に伸ばしたら90度回転させ、また縦に伸ばして円形にする。



最初に伸ばしたときに皮の直径を決め、90度回転させてからもう一度、同じくらいの力で伸ばすと整った円形になります。もっと大きいサイズにしたいときは、再びこの一連の作業を行いましょう。ちなみに、撮影時に作った皮は直径9〜10cm。厚みが割とありますが、さらに薄くなるとちぎれやすくなるため、このサイズを目安としてください。なお、餃子の皮のように小さいものを伸ばすときは、めん棒も小さく細いほうが扱いやすくなります。

東山さんの使う写真のめん棒は、直径2cm×24cmの小さめサイズ。

直径9〜10cmの丸い皮に成形できました。なお、東山さんのレシピでは、皮の厚みは均一。端と真ん中で差をつけないスタイルです。
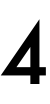
- 肉あんをトングなどでつかみ、生地の中央へ載せる。

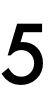
- 人差し指を水でぬらし、生地の外周の半分に塗る。

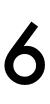
- 肉あんを中指で押さえながら生地で包み、生地が重なり合った部分を指でしっかり圧着させる。



肉あんに触れるのは中指だけと決め、この指で皮を触らないようにすると、何個包んでも皮がきれいな状態を保てます。皮の重なる部分は、中央から両端に向かって押さえながら閉じるだけ。餃子のひだは皮と肉あんの隙間をなくすためのものですが、この皮は伸びがよくて肉あんがピチッと収まるので、ひだを作る必要はありません。閉じたところの厚さが均一となるため、一部だけ固くなることもなくなります。
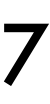
- 作業台に置き、底になる面を作りながら、餃子らしい半月状になるように形を整える。



平らな場所に置き、両手で端を持って手前に少し湾曲させるのがコツ。同時に底部分も平らとなり、自立するようになって扱いやすいうえ、ムラなくきれいな焼き目がつけられます。

にらは水分が少なく、液体調味料もそれほど使っていないので、包んだ状態で時間が経ってもベタつきにくいのが特徴。打ち粉をふってラップをかけておけば、冷蔵庫で一晩の保存も可能です。
焼き方

- 湯を沸かしておく。

- フライパンに油を引き、火はつけずに餃子を並べる。


点火する前に餃子を載せることで、焼きムラが抑えられます。たくさんの量を一気に焼こうとして、詰め込みすぎるのは避けて。餃子同士がくっつき、分けるときに皮がはがれて肉汁が流れ出てしまいます。
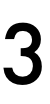
- 強火にかけて、焼き面からチリチリと音がするまで待つ。

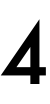
- 音がしてきたら、湯160mlを正確に計量して加える。

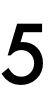
- すぐにふたをして、強火で3分間加熱する。

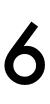
- ふたを外し、中火にして余分な水分を飛ばす。


水分を蒸発させている間は時折、フライパンの向きを変えましょう。火の入り具合が均一になることで焼きムラが抑えられ、きれいに仕上がります。
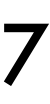
- 水分が飛んだら焼き色をチェックし、きつね色になっていたら火を止めて盛り付ける。


焼き上がりに油を回しかけても、きれいな焼き色が付きます。ただし、肉あんにラードを多く使っている場合は油っぽくなってしまうので、今回のレシピではおすすめしません。

こんがりきつね色に焼き上がった餃子。パリパリの皮は小麦粉の甘みが感じられ、ジューシーな肉あんとの相性も抜群です!
味変で楽しむ!
たれのレシピ3選
定番のしょうゆ+酢+ラー油もいいけれど、たまには違う味も楽しみたい……。そんな気持ちに応えて、東山さんがオリジナルのたれを教えてくれました。キッコーマンの調味料を活用したオリジナルたれは3つ。もちろん、混ぜる割合はお好みで。複数のたれで味変しながら食べたら箸が止まらなくなって、あっという間に完食してしまいそう!

『さわやかしょうが白だし』
しょうゆの代わりに 『キッコーマン 旨みひろがる 香り白だし』を使い、酢と混ぜ合わせてアクセントにおろししょうがをプラスしました。餃子のたれと言うとパンチの効いたものが多いですが、こちらはさっぱりした味わい。白だしは濃縮たれなので、酢と合わせても物足りなくなりません。東山さん曰く「残り2つのたれとは路線の違う、リセッタ—的な存在」。

『バリバリ黒こしょうステーキしょうゆ』
東山さんもお気に入りのステーキ専用調味料『キッコーマン ステーキしょうゆ あらびきおろし』に、あらびき黒こしょうを加えるだけ。ストロングな味の餃子と合わせても互いに負けることなく、黒こしょうの風味がそれぞれの味を上手につなげてくれます。

『生にんにく焼肉だれ』
『キッコーマン わが家は焼肉屋さん 中辛』に、すりおろした生にんにくを加えてパンチを効かせた1品。本場中国のように、肉あんではなくたれに加えることで、にんにくの鮮烈な風味がたっぷりと味わえます。「いろいろな人に好まれるようにと中辛を選びましたが、『わが家は焼肉屋さん』シリーズはどれもおいしくできました」と、東山さん。

よくある失敗と
解決法に関するQ&A
(東山さんに聞きました)
餃子にまつわるよくある疑問に、東山さんが一問一答形式で答えてくれました!
Q.きれいに焼き色がつかない。コツはある?
A.
焼くときは、冷えたフライパンに餃子を並べてから火をつけましょう。餃子はくっつきやすいので、フライパンはテフロン加工のものか、きちんと手入れされている鉄製を使うのがおすすめ。一度にたくさんの量を焼かないようにすることも大切です。また、皮から作る場合は、餃子の底を平らにすることで焼きムラが抑えられ、焼き色がきれいに付きます。
Q.皮が破れたり、肉あんがはみ出したりしてうまく包めない。きれいに包むコツは?
A.
基本的に、皮の大きさと肉あんの量のバランスがとれていればきれいに仕上がるので、まずは計量すること。今回のように、レシピに重量が記載されている場合はそれに則りましょう。市販の皮を使うなら、皮の大きさにもよりますが肉あん20gが目安となります。
Q.合いびき肉と豚ひき肉、どちらのほうがおすすめ?
A.
牛肉は香りが強いため、餃子には豚肉のほうが向いています。なお、肉あんを作るときは冷蔵庫から出してすぐのものを使いましょう。常温の豚肉は脂が溶けやすいため、ベチャッとした肉あんになってしまいます。
Q.市販の皮を使って作るときのコツは?
A.
まず、皮の大きさに合わせて、肉あんの量を20gくらいに調整してください。市販の皮は手作りのものより薄いため、湯の量も減らしましょう。今回のように5個焼く場合は、100mlを目安に調整を。
パリパリ&じゅわっ!
たっぷりのおいしさが
詰まった自家製餃子を
楽しもう
今回、教えてもらったレシピは、「僕が知る限り、一番簡単な手作り餃子」と、東山さん。皮の加水率も綿密に計算したことで小麦粉と水がをバランスよく配分され、おいしくて包みやすい皮が完成したそうです。
「ひと口食べたときに小麦のおいしさが感じられる皮で、じゅわっとあふれる肉汁もしっかり受け止めてくれますよ。ご紹介したオリジナルのたれはしっかり味の餃子に合うので、ぜひ試してみてくださいね」(東山さん)

教えてくれた人 東山広樹さん
東京農業大学醸造科学科を卒業後、人材派遣会社を経て、料理書専門出版社に転職。料理の知識を深めた後、汁なし担々麺専門店『タンタンタイガー』を創業。現在は株式会社マジでうまい代表取締役として、レシピ開発や会員制レストラン主宰などを中心に活動する。2025年5月に東京・神保町で開業した『餃子の肉太郎』も人気。近著に『マニアック家中華』(ダイヤモンド社)がある。



























































































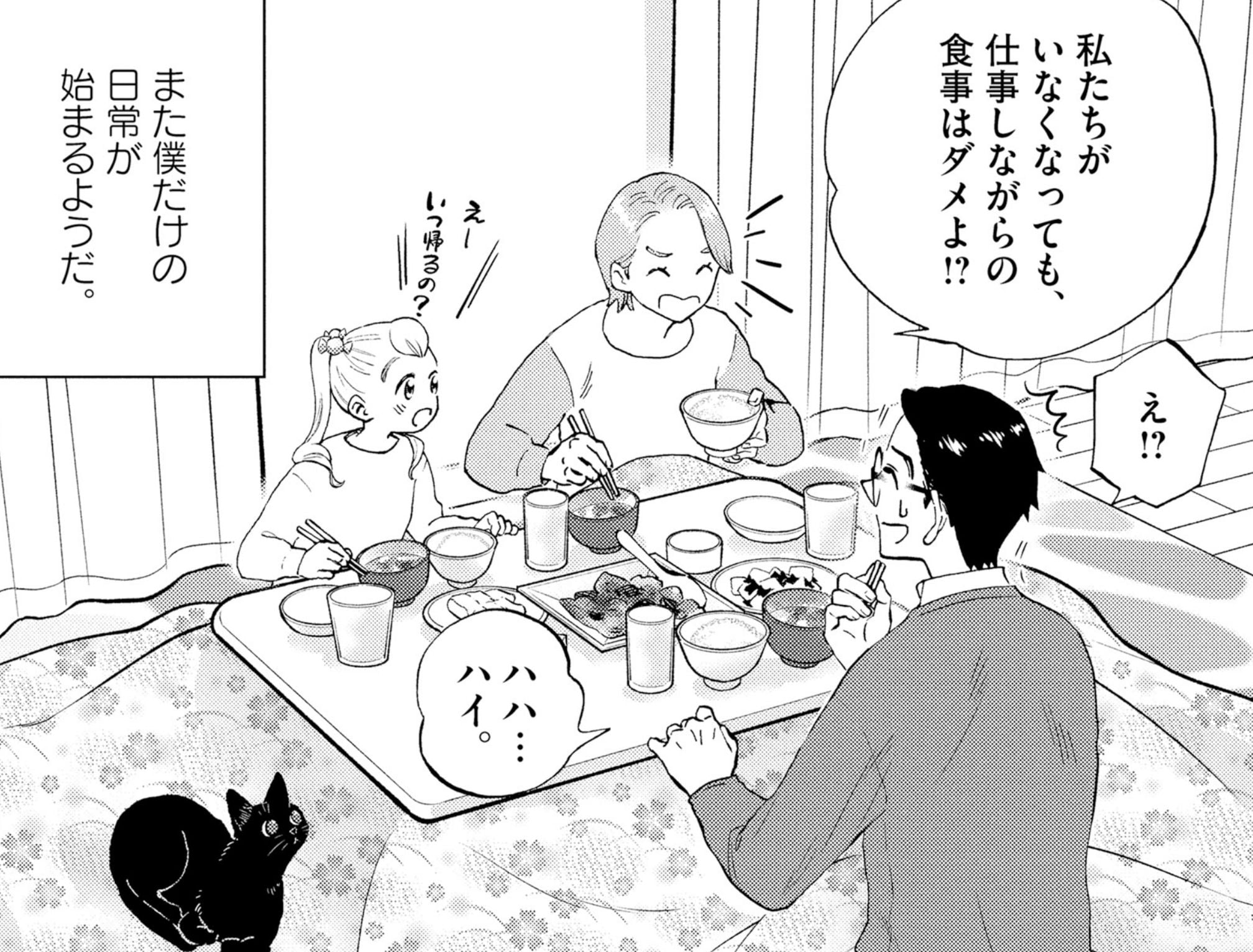





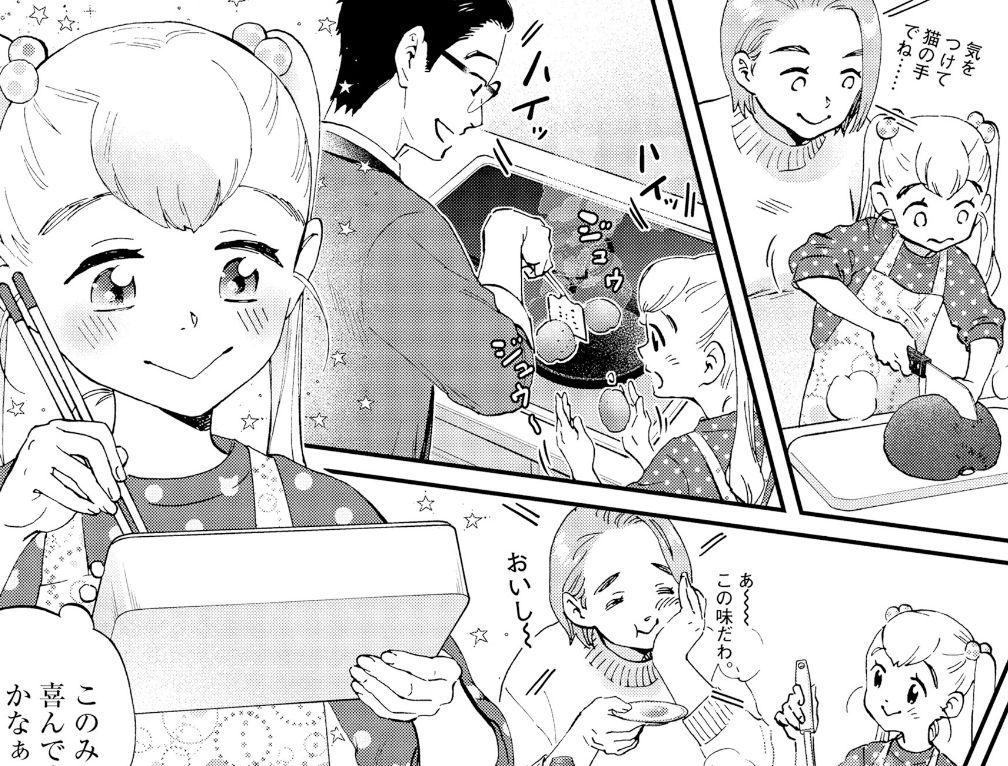







































































































































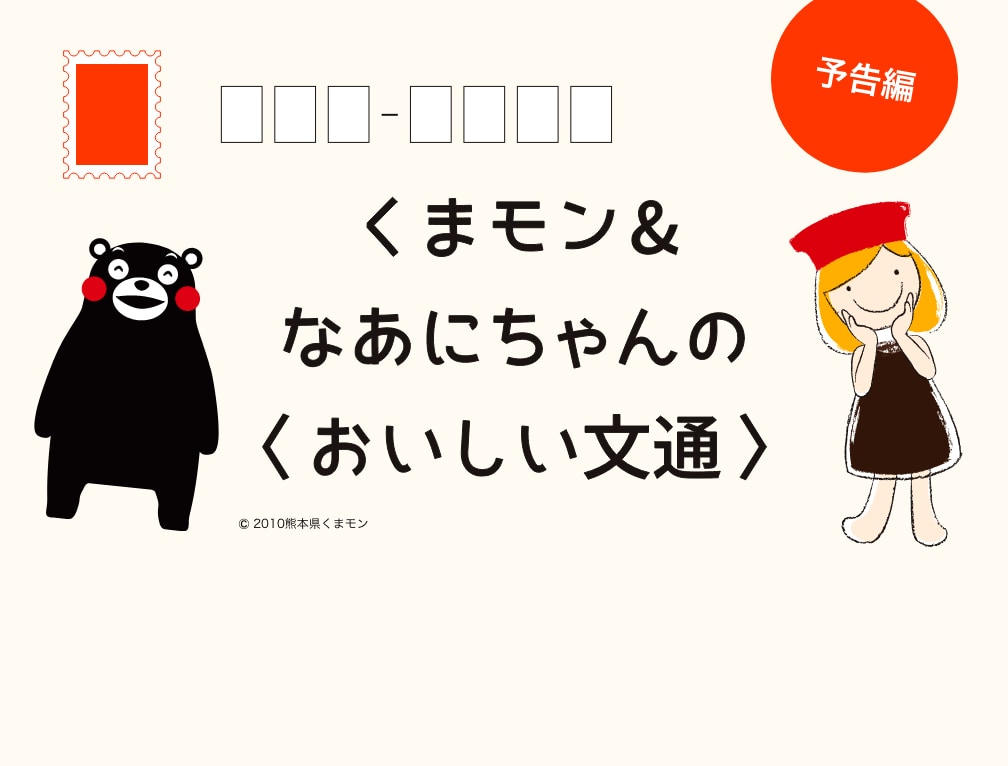





































ホームクッキング編集担当より
撮影で特に印象に残っているのは「計量」の重要性。料理をしていると、多少の誤差は気にせず進めてしまいがちですが、基本に立ち返るような気づきでした。今回東山さんにご紹介いただいたレシピは、ひと口食べた瞬間に肉汁がじゅわっと広がり、「家でこんなにおいしくできるの!?」という驚きと感動が詰まっています。餃子って、食べると元気が湧いてくる気がしませんか?ぜひみなさんも餃子を作って、食べて、パワーの源にしてみてくださいね。(編集担当・大津)