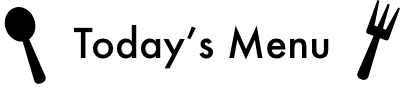
ズッキーニは生で食べられる?
おすすめの食べ方や
保存方法を紹介

一見、きゅうりにも似た姿のズッキーニですが、実はかぼちゃの仲間。日本で食べられるようになったのは1980年代ごろと比較的新しいものの、イタリア料理ブームなども追い風となり、今ではすっかり定着しました。もちろん、イタリア料理以外にも使い道はさまざまで、しょうゆとの相性も抜群!そんなズッキーニをさらに活躍させるために、食べ方や調理のコツ、保存方法といった情報をまとめました。おすすめレシピとつくり方のアドバイスもぜひご活用ください。
生で食べられる?
ズッキーニの食べ方と
調理のコツ
ズッキーニは生食してもいい?
油で炒めたり、煮込んだりするイメージが強いズッキーニですが、アクがそれほど多くないため、生の状態でも皮ごとおいしく食べられます。そのみずみずしさを楽しむためにも、できるだけ新鮮なものを選びましょう。なお、食感やえぐみが気になる場合は、皮をむいたり、薄切りにするのがおすすめです。
生で食べる際の下処理
料理に合わせて切ったら水にさらし、3~4分おいてから使うようにしましょう。カットしたままだと断面からぬめり成分が出て、ズッキーニ同士がくっついてしまいます。
おすすめの食べ方と加熱調理のポイント
洋食のイメージが強いズッキーニですが、淡泊な味わいなので和風の料理にもよく合います。油との相性が良いうえ、淡色野菜の中では多く含まれるカロテンの吸収をよくするという点でも、油を使った調理法がおすすめ。
炒める
普段の料理より油を多めに使い、やや強めの火加減でしっかり加熱すると白い部分がとろっとしておいしくなります。加熱時間が長すぎると水分が逃げ、ジューシーさを失ってしまうのでご注意を。
揚げる
170℃~180℃の油温で素揚げしたものを揚げびたしにしたり、炒め物に後から入れたりすると鮮やかな色を保てるうえに、香ばしさもアップ。薄すぎるとすぐに火が通り過ぎますが、1.5cmほどの厚さにカットすれば、外側しっかり、中はとろりと2つの食感が楽しめます。
煮込む
ズッキーニをじっくりと煮込むことでとろりとした食感となり、スープに溶け出したうまみまでしっかり味わえます。小さくカットすると煮込んでいるうちに溶けてしまうので、大きめに切るようにしましょう。輪切りだけじゃない!料理によって使い分けたいズッキーニの切り方
ズッキーニは切り方を変えると、見た目や雰囲気も変化します。メニューに合わせて使い分ければ、ズッキーニ使った料理がさらにランクアップすること間違いなし!

左から時計回りに、ボート型、乱切り、拍子木切り風、さいの目切り、輪切り、リボン状にしたもの。

縦半分に切ってボート型にしたものは、断面の真ん中をくり抜いて肉だねなどをこんもりと詰め、グリルで焼くと存在感のある一品に。味なじみがよくなる乱切りは、炒め物におすすめです。1/3の長さにカットし、4つ割にした拍子木切りのような形のものも炒め物に合います。ズッキーニはなすとの相性も良いので、切り方をそろえて麻婆なすなどに使っても良いでしょう。
ラタトゥイユなどに使うなら、1~1.5cmほどのさいの目切りに。輪切りの厚さはお好みですが、ピーラーなどで皮をしま状にむいてから厚めの輪切りにしたものをソテーすると、見た目に華やかで肉料理のつけ合わせにもぴったりです。ピーラーで薄くリボン状にしたものは、生のままサラダで。
ズッキーニを長持ちさせる
保存方法
(常温・冷蔵・冷凍)
みずみずしさが魅力のズッキーニは、乾燥に弱い野菜。水分が抜けると味が落ちてしまうので、できるだけ乾燥させない工夫が必要です。
常温保存
カットしていない丸ごとのズッキーニは、夏を除く時期なら常温保存が可能です。乾燥を防ぐためにキッチンペーパーで包み、食品保存用のポリ袋に入れて風通しの良い冷暗所に置きましょう。保存期間は3~4日が目安。


ズッキーニは乾燥と冷やしすぎに注意を。
冷蔵保存
ズッキーニを冷蔵保存する際は、ラップでしっかり包んで。立てた状態で冷蔵庫の野菜室に入れます。保存期間は丸ごとの状態なら4~5日、使いかけなら3~4日が目安。


使いかけのズッキーニは、特に乾きやすい断面もラップでしっかりと覆いましょう。

冷蔵庫の野菜室は、冷蔵室に比べて温度が高め。ズッキーニは低温に弱く、冷蔵室だと冷えすぎてしまうため、野菜室での保存が適しています。
冷凍保存
使い切れなかったり長く保存したりする場合は、使いやすいサイズに切った状態で冷凍しましょう。カットしたズッキーニはジッパー付き保存袋に入れ、冷凍室へ。ズッキーニ同士がくっつくと取り出しにくいので、袋に入れるときは重ならないようにしましょう。使うときは、解凍不要で調理できます。

金属トレイに載せるとすばやく凍らせることができます。

冷凍したズッキーニは約1か月と、長期で保存できます。ただし、生の状態に比べてシャキシャキ感が落ちてしまい、生食には不向き。炒め物や煮込み料理に使うのがおすすめです。
なお、丸ごとの状態で冷凍する方法も。ラップに包んでジッパー付き保存袋に入れ、空気を抜いて口を閉じたら金属トレイにのせて冷凍室へ。使うときは常温で15分ほどおくと、包丁でサクッと切れます。丸ごと冷凍したものは食感が大きく変わるので、煮込み料理などに。
新鮮でおいしい
ズッキーニの選び方
ズッキーニの鮮度を見分けるなら、全体のハリ感とヘタの切り口に注目しましょう。全体的にしわが出てきたものは、収穫から時間が経って水分が抜けている可能性が。また、ヘタの切り口が茶色になっていたり、やわらかくなったりしていたら鮮度が落ちている目安です。また、健康的に育ったズッキーニは緑色が濃く、太さが均一。大きすぎるものは育ちすぎて固くなっている可能性もあります。

皮はどうする?
どんな種類がある?
ズッキーニに関するFAQ
ズッキーニを使うときに浮かびがちな疑問は、ここでスッキリ解消しましょう!
Q.ズッキーニの皮はむくべき?
A.
基本的には皮付きのまま食べられますが、大きく育ちすぎると固くなることも。気になる場合はピーラーでむいてから調理すると、食感が良くなりますよ。

ピーラーを使えば、力を入れずにするんとむけます。
Q.黄色いズッキーニや丸いズッキーニもあるの?
A.
一般的な細長くて緑色のもの以外にも、ズッキーニにはさまざまな種類があります。細長くて黄色いタイプのほか、形状がずんぐりとした「丸ズッキーニ」、円盤形の「UFOズッキーニ」なんてものも。また、開花前の花を付けたのは「花ズッキーニ」と呼ばれており、花の中に肉だねなどの詰め物をして揚げるのがポピュラーな調理法です。

鮮やかな色が印象的な黄色いズッキーニ。緑色のものに比べて皮がやわらかく、味もより淡泊です。

くせのない味わいの花ズッキーニは鮮度が落ちやすいため、流通量が少ない希少な食材。
Q.火の通り具合を見分ける方法は?
A.
ズッキーニは火が通っても、見た目の変化が出にくい野菜。生食できるので多少、加熱不足でも問題ありませんが、気になる場合は竹串を刺して固さを確認しましょう。好みの食感に仕上げるためにも、一度試してみるのがおすすめです。
いつもとはひと味違う!
ズッキーニを使った
おすすめレシピ3選
ズッキーニの魅力を引き出す人気のレシピ3品をご紹介!シンプルな使い方でも、ズッキーニの存在感が際立つものばかりなので、ぜひお試しください。
豚バラとの組み合わせでボリュームたっぷり!
『ご飯がすすむ!甘辛だれのズッキーニ肉巻き』

みりんと砂糖のどちらも使うことで、ジューシーなズッキーニに負けないこっくり味に。ズッキーニは下ゆで不要で、ただ切るだけという手軽さも魅力です。
ズッキーニは豚バラの脂とも相性抜群!全体に薄力粉をまぶしてから焼くため、たれが脂に弾かれることもなく、しっかりとからみます。大人が食べるなら、アクセントとして七味をかけるのもおすすめ。巻いた肉がはがれないように、巻き終わった箇所から焼くのがポイントです。
くるんとしたリボン状の見た目も楽しめる
『生がおいしい! ズッキーニサラダ』

薄くむいたズッキーニの食感が小気味良いサラダ。緑×白のコントラストとレモンの香りが涼しげで、暑い時期にもぴったりです。
ズッキーニとしょうゆの相乗効果でグンとおいしく!
『ズッキーニのしぼ生ステーキ【味つけは生しょうゆだけ】』

しょうゆひとつで、ズッキーニがごちそうに!かめばズッキーニとしょうゆのうまみがジュワッとあふれ出て、口いっぱいに広がります。
和洋中に合うズッキーニを
使いこなして、
レパートリーを広げよう!
切り方や食べ方を変えることで、おいしさの幅がどんどん広がるズッキーニ。ただ焼くだけ、味つけはしょうゆだけ、というように、調理法がシンプルなほど淡泊な味わいが引き立ちます。和洋中、さまざまな料理に合ううえに、色味がきれいで食欲をそそるので、もっと活躍の場を増やしてみてはいかがでしょうか?

教えてくれた人 野口英世さん
料理研究家、フードスタイリスト、 All About「簡単スピード料理」ガイド 。無理や無駄のない、つくり手重視の効率的なレシピとスタイリングアイデアにファンも多く、テレビや雑誌、新聞、広告などで活躍中。近著に『turk フライパンクックブック』『使いやすい台所道具には理由がある』(ともに誠文堂新光社)などがある。
撮影/金田邦男
公開:2025年5月20日



























































































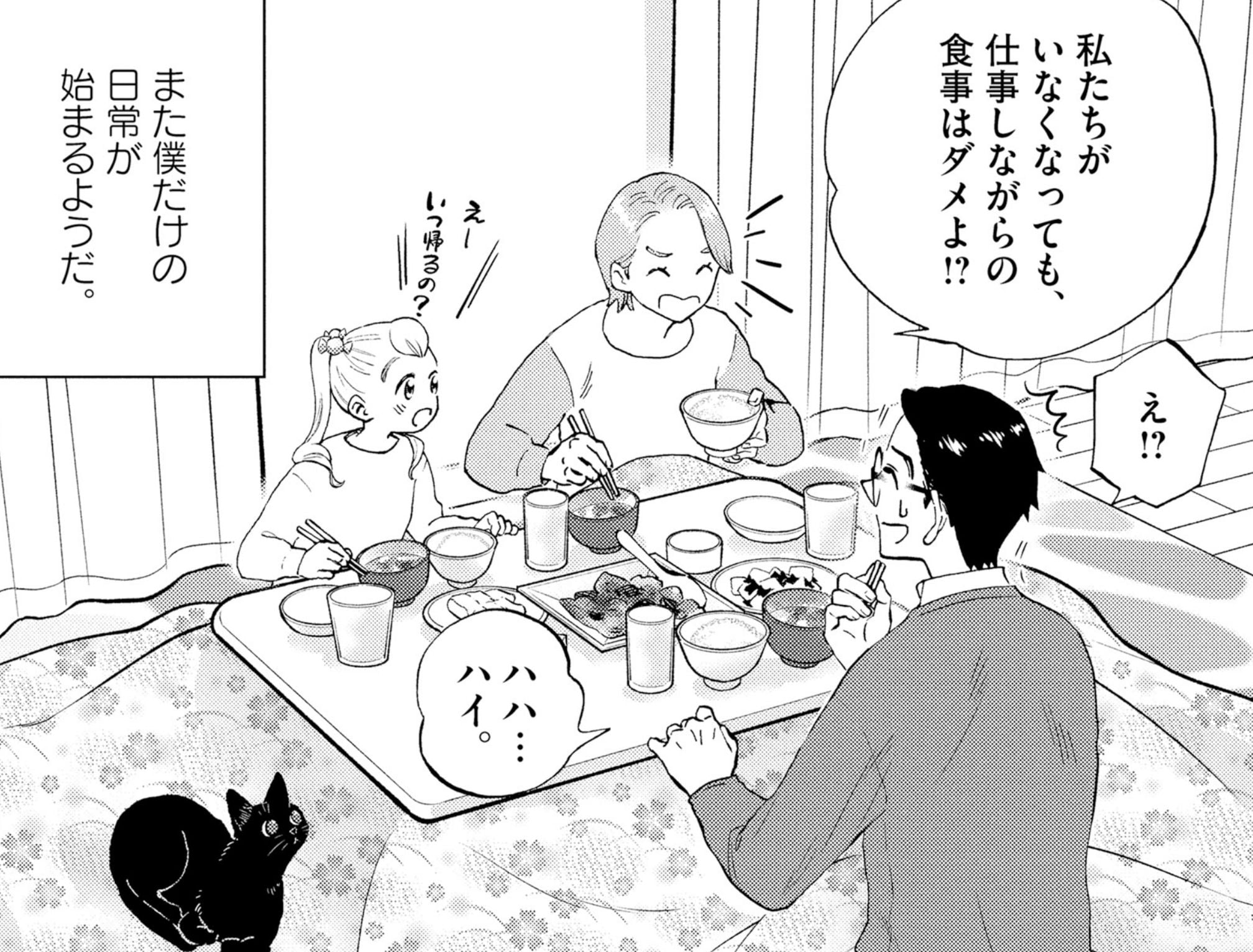





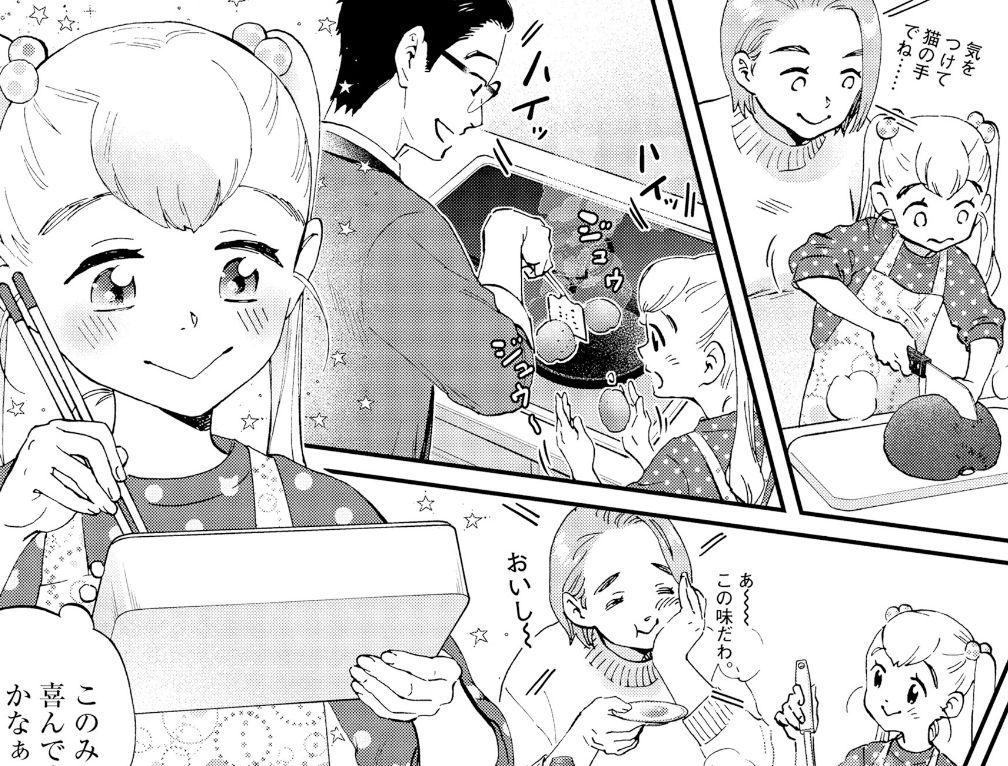







































































































































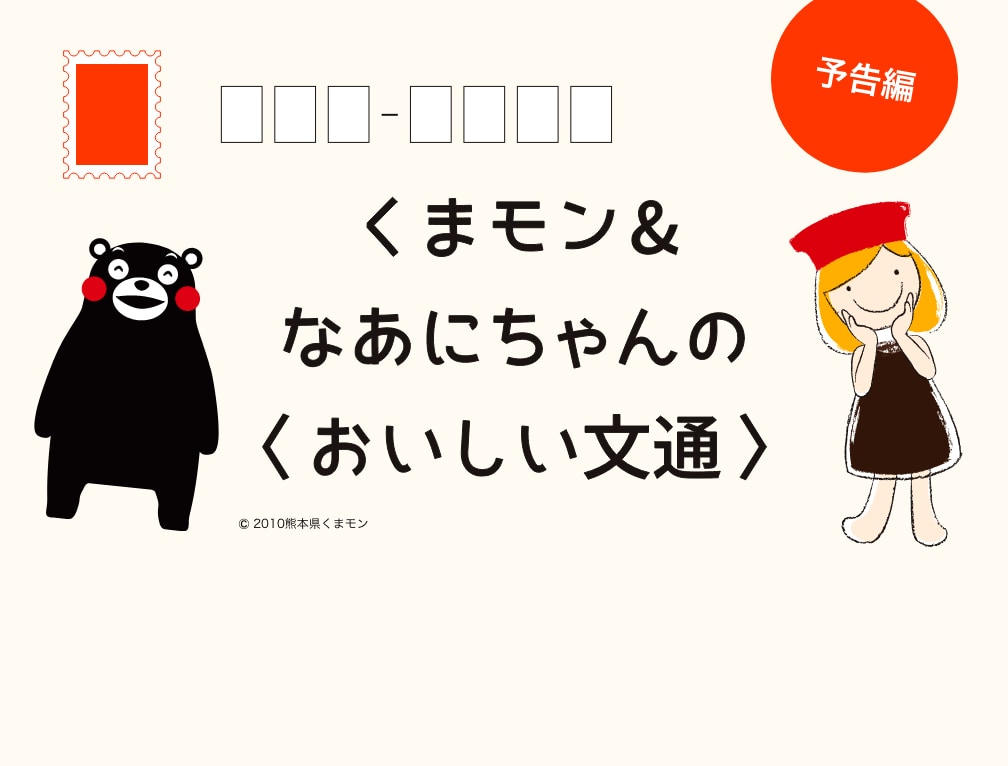





































ホームクッキング編集担当より
太陽の光をいっぱい浴びた濃い緑色のズッキーニが店先で並んでいると、ついつい手に取りたくなりますよね。調理法によっても食感が様変わりし、いくら食べても飽きないので、わが家ではなすと肩を並べるほどの夏の定番野菜です。ご紹介した「 ズッキーニのステーキ 」はしぼ生(しぼりたて生しょうゆのキッコーマン社内での愛称)だけで完成する、素材のおいしさをたっぷり味わえるレシピ。SNSでも「簡単なのにおいしい」と毎年人気なのでぜひお試しください♪(編集担当・市川)